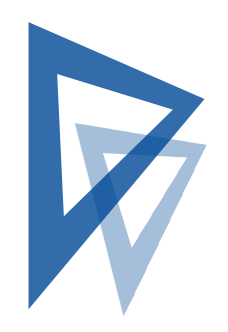第1回バイオインダストリー大賞受賞、京都大学高等研究院 本庶 佑 特別教授インタビュー
 2017年、(一財)バイオインダストリー協会(JBA)は、創立30周年を迎えた。これを機に、次の30年を見据えて、"最先端の研究が世界を創る―バイオテクノロジーの新時代―"をスローガンに、「バイオインダストリー大賞」「バイオインダストリー奨励賞」を創設。6月、選考委員会が開催され、大賞には京都大学高等研究院 本庶 佑特別教授が、奨励賞には10人の研究者が選出された。編集部では京都大学大学院医学研究科の研究室を訪ね、PD-1研究の背景と苦労、基礎研究への想いや今後の課題を聞いた。
2017年、(一財)バイオインダストリー協会(JBA)は、創立30周年を迎えた。これを機に、次の30年を見据えて、"最先端の研究が世界を創る―バイオテクノロジーの新時代―"をスローガンに、「バイオインダストリー大賞」「バイオインダストリー奨励賞」を創設。6月、選考委員会が開催され、大賞には京都大学高等研究院 本庶 佑特別教授が、奨励賞には10人の研究者が選出された。編集部では京都大学大学院医学研究科の研究室を訪ね、PD-1研究の背景と苦労、基礎研究への想いや今後の課題を聞いた。
「多くの芽を出すには、たくさん種をまかなきゃいけない」
◇ 一番苦労したのは、PD-1分子の機能解明
 ◆この度のバイオインダストリー大賞受賞、おめでとうございます。ひとことご感想をお願いします。
◆この度のバイオインダストリー大賞受賞、おめでとうございます。ひとことご感想をお願いします。
本庶: 第1回バイオインダストリー大賞を受賞し、大変光栄でうれしく思っております。私の研究がいわゆる"バイオインダストリー"につながるのかどうかと思いましたが、ずっと基礎研究にたずさわってきて、結果として産業化につながったということですので、基礎研究者でもこういう機会があるということが、若い研究者を元気付けられることになればよりうれしいことだと思っています。
◆受賞業績の"PD-1の発見とその機能の解明"の研究で、ブレークスルーを遂げられた一番のポイントは何だったのでしょうか?
本庶: 免疫によってがんを治すという試みは、過去からありました。日本では古くは丸山ワクチン、世界中でもいろいろな方ががんワクチンなどに取り組まれましたがうまくいかず、それでも免疫学者は漠然とがんは異物だから免疫で治るはずだ、と考えていました。でも、なかなかうまくいかなかった。今から思うとその原因は、免疫系に非常に強いブレーキが掛かっている状況だったのです。そこで一生懸命アクセルを踏んでも、車が前に進まないという状態で、それまでの多くの研究では、アクセルをもっと噴かせることを一生懸命やってきて、どうしてもがんをやっつけることができなかった。私どもが1992年に発見したPD-1は、その機能の解明を遺伝子の破壊実験でやってきて、1997年から1998年にそれが免疫系のブレーキ役だということが分かりました。
免疫のブレーキ役という分子は、あまり多くは知られていませんでしたので、私たちはブレーキをブロックして、免疫を活性化するという新しい方法でやってみようと試みました。そこに目を付けた理由は、一般的なそういうアクセルとブレーキの関係以外に、PD-1という遺伝子を壊したネズミがゆっくりと病気になるんですね。つまり副作用が起こっても、そんなに急激なものではないだろうと考えて、これは薬として使える可能性が高いんじゃないかと。それでネズミで実験を実施し、うまくいったということでしたね。
◆その際に、先生ご自身が注力され、苦労されたことは何でしょうか?
本庶: PD-1の機能が免疫ブレーキ役と分かり、それを壊してみようと研究に力を入れました。ただ、非常に運がよく、それほど大きな苦労はしなくて済み、うまくいったんですよ。むしろ一番苦労したのは、分子を見つけてその機能がブレーキ役だということを解明するまでで、約6年かかりました。なぜかというと、PD-1を用いる実験ではその症状が軽微なのです。逆にCTLA-4という、PD-1と並ぶ免疫のチェックポイント阻害剤といわれる分子があるのですが、そのCTLA-4遺伝子を壊したネズミは4~5週間で全部死ぬ。それぐらい激烈な作用があると分かり、逆に、これは薬にはならないだろうと考えていました。こんな副作用が強いと、臨床には向かないだろうと思っていたんですが、今、薬になっています。
◇ 米国・ベンチャー企業の決断が実用化の鍵となった
 ◆その後、企業との共同研究で、がん免疫療法として実用化へと導いて行かれたのですが、最も大変だったことは何ですか。また、それを、どう乗り越えてこられたのでしょうか?
◆その後、企業との共同研究で、がん免疫療法として実用化へと導いて行かれたのですが、最も大変だったことは何ですか。また、それを、どう乗り越えてこられたのでしょうか?
本庶: どこの製薬企業も乗ってこなかったということですね。(特許共出願の)小野薬品は、がん治療薬の経験がなかった。がん治療薬を開発するのはやっぱりリスクが高いから、とても1社ではやれないと言っていたんですね。それで彼らは日本のほとんど全メーカーを回り、共同研究を依頼したのですが、どこも引き受けない。それで1年ぐらい経過してから僕のところに来て、手を引くと言ってきたんです。それで私は、自分でやろうと思ってアメリカに行き、シアトルにある友人のベンチャー企業に直接相談に行ったら、こっちが拍子抜けするぐらい非常にあっさりと、"すぐにやろう"と返事があった。その後、そのベンチャーと一緒に単独で進めようとしていましたが、約3カ月後に突然、小野薬品から共同でやりたいとの提案があったのです。
◆そのベンチャー企業と、共同研究がうまく進めることができた要因は何だったのでしょうか?
本庶: 別のベンチャー企業・メダレックス社が、私と小野薬品の共同出願特許が公開されたのを見て、小野薬品に直接共同研究を申し込みました。メダレックスはもともとヒト型の抗体をネズミで作る技術を持っていたので一気に研究が進んだのです。さらに、当時メダレックスにいて現在、ブリストル・マイヤーズ社(BMS)のバイスプレジデントになっているNils Lonberg氏は、実は私の古くからの友人だった。ですので、その後は非常にスムーズにことが運びました。ひとつ大きな転機は、2008年にBMSがメダレックスを買収したことです。2006年くらいから治験が始まっていて、非常に効果がありそうだということを、BMSが聞きつけて買収したのです。そこからほとんど苦労はなかったですね。
◇ いっぱいチャンスをつくらないと、いい結果は得られない
◆PD-1のような大きな発見で、世界の医療・医薬品分野を変革した事例は数少ないと思いますが、本庶先生が研究を進める中で常に心がけておられることは何でしょうか?
本庶: 私の研究スタイルは何かに応用するために研究するのではなくて、基本的に基礎研究なんです。基礎研究で何か新しいことが見つかったときに、何か役に立つ道はないかと考えるので、企業の研究とは逆ですよね。企業は何かの治療の薬剤を見つけたいから研究するスタイルでしょう。基礎研究とは、特にバイオロジーはいわゆるエンジニアリングとは違って、分からないことが山ほどあるから、想定外のことがたくさん出てくる。効くと思った薬が別のところに効いてということが日常茶飯事なのです。
しっかり基礎研究をやってきて、そこから出てきたものが意外と応用に結び付いて、可能性が広がったという例は日本でもたくさんあります。そのために、種をたくさんまかなきゃいけない。その中から芽が出るのは10分の1しかないし、そこから葉が出て実になってその果実がうまいとも限らないのです。ですから、「いっぱいチャンスをつくらないといい結果は出ない」、といつも言っています。PD-1は正直、本当に運がよかったと思います。僕は、最初からこれで病気を治してやろう、と思って研究したことは一度もなかったのです。
◇ シーズの評価力を高める必要がある
 ◆基礎研究の成果を応用に結び付けるのは主に企業の役割ですが、企業サイドの課題はどう考えられますか?
◆基礎研究の成果を応用に結び付けるのは主に企業の役割ですが、企業サイドの課題はどう考えられますか?
本庶: 最近、日本の製薬企業はちょっと厳しいのではないかと考えています。研究所を縮小し、アウトソーシングを推進する傾向があるけれども、アウトソーシングするには丸投げでは出来ない。世界中の情報網を駆使して、大学や他の研究機関のいろいろなネタ(研究のシーズ)を評価しなければいけないのです。バイオロジーというのは、やってみないと分からないから、一種のギャンブルなんですよ。ということは、われわれはいろいろなことに手を出さなきゃいけない。ずっと研究を続けても、必ず橋が架けられますという話では全然ないんです。ですから、企業は規模を大きくして中の人材を厚くし、経営トップにバイオロジーの分かる人がいてほしい。大きな資本を持ち、チップをいっぱい払わないと当たらないですよ。かつて日本の薬学はケミストリーを重視し、有機合成でいろいろなキャンディデートをつくる方法だった。デリバティブをいっぱい作ってずっと成功してきたけれども、いまやバイオロジーの時代。バイオロジーは、以前は薬学全体の3分の1ぐらいでしたが、これを増やして人材を育てないと大変だと思いますね。
◇ アカデミアと企業をつなぐ専門家と研究への投資が課題
◆では、そのような研究のタネを基に産業化を進めて、日本の大学、企業が世界に貢献できるようになるための課題については、どのように考えておられますか?
本庶: 私は、日本のアカデミアは結構レベルが高いと思うんですね。ただ、研究者自身が意外と気が付いていない。こういうふうに利用できるという種を持っている人は結構いるのです。それで、AMED等ができて、アカデミアとインダストリーをつなぐ試みはあるが、インダストリー側から見てアカデミアのシーズの中身が見えない、あるいは評価力がちょっと弱いんではないかと思います。加えて、アカデミアも売り込むのが下手ですよね
アメリカの場合は、売り込みのプロがいる。つまり、研究者は自分で売り込みなどやりたくないんですよ。知財部門でそういうことに携わる人は、大学で知財を取ったら、それをライセンスするために売りに行くわけです。単に、パテントを抱えていてもまったく意味がないから。そういう仕組みが日本ではうまくできていません。
逆に、日本の企業は、欧米の売り込みに簡単に飲み込まれて、何千億円もの買収を多くしている。あれだけの資金を日本の大学に出したら、僕はもっと成果が生きると思う。欧米では、ベンチャー企業は、それがモノになるかならないか分からないという存在です。だからベンチャーなんですよ。それを売っているわけだから、半分はだまされる覚悟で考えなきゃいけない。例えば数千億円の大型買収をやるとしたら、例えば京大に同じ額の数千億円のファンドを積んで、その代わりに成果が出たものは、全部その会社にエクスクルーシブライセンスを渡すなど、といった方がはるかに双方の得る果実が大きいと思います。そう考えて企業は、アカデミアをもう少しうまく使った連携をした方がいいと。何千億円出すんだったら、日本のアカデミアに出して、それに対して正当なシーズをもらう形で、双方ウィン・ウィンの関係にすべきだと思いますね。そこが非常に欠落しているような気がして、課題だと思います。
◆将来、PD-1を含めて、先生が進めておられる研究は、どのような方向を目指しておられるのでしょうか?
本庶: 私は基本的に自分の興味のままに研究をやってきました。これからもっと新しい何かを見つけるというよりは、応用面でいうとPD-1について以前、イギリスの科学雑誌『ニュー・サイエンティスト』の記者が書いていた、"これはがんにおけるペニシリンだ"という言葉のとおり。イギリス人っていい表現をしますね。要するにペニシリンで感染症は劇的に変わったけれども、全部治ったわけじゃない。ごく一部ですよね。それでもペニシリンができたことによって次々と抗生物質が広がっていって、最終的に感染症の大部分は克服できたんだと。この免疫治療で治るがん、治る患者さんが出てきたけれども、治らない人もいっぱいいるわけです。それをどうやって治すかということが一番重要なのですよ。そのために、PD-1をテコにして次々と展開していくというのが一番の近道だと思っているんですけどね。そういう方向で今研究を進めています。
◇ 若者は「打席に立ち、思い切りバットを振ったかどうか」だ
 ◆最後に、JBAでは、大賞と同時に「バイオインダストリー奨励賞」を創設し、若い研究者を支援する活動も行っています。次世代を担う研究者たちにメッセージをお願いします。
◆最後に、JBAでは、大賞と同時に「バイオインダストリー奨励賞」を創設し、若い研究者を支援する活動も行っています。次世代を担う研究者たちにメッセージをお願いします。
本庶: 研究者も40歳になると完成されているので、若いというと30代でしょうね。結局、人生は1回きりですから、どうやって死にたいかということなんですよ。2回は死ねないでしょう(笑)。だから人生の最後に、自分なりに「ああ、自分は好きなように生きたな」と思えるかどうか。人それぞれいろいろなことがあるから、そのときに何で満足するかということじゃないですか。打席には立たせてもらわないといけないけど、ホームランが出るとは限らない。しかし、思い切りバットを振ったかどうかですね。ですから、僕がもし、悩み多い若い研究者にアドバイスすることがあるとしたら、本当に自分は何がしたいのかを自分で考えて、やっぱりそれをやった方がいいよと言いますね。
―心に響くメッセージですね。若い人たちが勇気づけられると思います。今日は、本当にありがとうございました。
(聞き手=JBA広報部 江口あつみ)